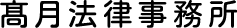まるっと六法
[Episode 1] ハンコは怖い!
「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)
「ここにハンコお願いします」、「ハイ(押印)」、日常、よくある光景ですが、うっかりハンコを押すと、あとあと大変な目に遭うこともあります。
Aが、「半年前に貸した1000万円を返せ。」と主張してBを訴え、これに対してBは、「カネなど借りていない。」とか、「すでに返した。」と主張して争っているとします。
このケースでは、誰の、どの主張が本当なのか、それによって、Aが勝つのか、Bが勝つのかが決まるということは明らかです。では、何が本当か、この判断のための資料となるのが証拠です。
例えば、「1000万円借用しました。」というB名義の借用書などの「文書」があれば、「カネなど借りていない。」というBの言い分は嘘っぽく、「貸した1000万円を返せ」というAの主張が認められそうです。しかし、この借用書のほかに、「1000万円受領しました。ただし、借入金返済のため。」というA名義の領収書があれば、「すでに返した。」というBの主張に分がありそうです。
もっとも、いくら借用書や領収書があっても、誰かが偽造したものでは話になりません。このため、借用書や領収書などの「文書」を証拠として用いるときは、冒頭に掲げたように、「その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)のです。
このときは、Aは、借用書は、真実、Bが作成した文書だということを、まず、証明しなければなりません。「成立が真正」とは、その文書が、作成者の意思に基づき作成されたという意味です。
では、それをどのようにして「証明」すればよいのでしょうか。そこで登場するのが、民事訴訟法228条4項の「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定です。これがあるので、「ハンコは怖い!」のです。
次回は、民事訴訟法228条4項について説明します。
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」(民事訴訟法228条4項)
「真正に成立した」とは、その文書が、作成者の意思に基づき作成されたという意味です。「推定」とは、甲という事実があれば、乙という事実があると一応、判断するという意味です。ここで「一応」と断ったのは、乙という事実は存在しないという証明がなされると、甲という事実があっても、乙という事実があるとは判断しないという余地があるためです。
話しを文書成立の真正に戻しましょう。上に示した民事訴訟法228条4項は、「本人又はその代理人の署名又は押印がある」(甲という事実に相当)ときは、私文書は「真正に成立したものと」一応、判断するといっているわけです。
AがBに、「半年前に貸した1000万円を返せ。」と主張し、Bが「カネなど借りていない。」と争ったので、Aが、B名義の借用書を証拠として提出したとします。このとき、Aは、この借用書という「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)わけですが、この借用書に、B「本人又はその代理人の署名又は押印がある」なら、民事訴訟法228条4項によって、この借用書は「真正に成立したものと」一応、判断されます。つまり、Aは、借用書の「成立が真正であることを証明しなければならない」という負担から解放されるわけです。Aにとっては、ありがたいことです。
とはいえ、この借用書は、本当は偽造文書で、「真正に成立したもの」ではないということもありえます。しかし、このときは、Bが、「真正に成立したもの」ではないことを証明しなければなりません。Bにとっては、迷惑な話です。証明も簡単ではありません。
だから、安易にハンコを押すと、後で大変な目に遭うことがあるのです。ハンコは怖いのです。このことは、また次回に説明します。
「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)
「ここにハンコお願いします」、「ハイ(押印)」、日常、よくある光景ですが、うっかりハンコを押すと、あとあと大変な目に遭うこともあります。
Aが、「半年前に貸した1000万円を返せ。」と主張してBを訴え、これに対してBは、「カネなど借りていない。」とか、「すでに返した。」と主張して争っているとします。
このケースでは、誰の、どの主張が本当なのか、それによって、Aが勝つのか、Bが勝つのかが決まるということは明らかです。では、何が本当か、この判断のための資料となるのが証拠です。
例えば、「1000万円借用しました。」というB名義の借用書などの「文書」があれば、「カネなど借りていない。」というBの言い分は嘘っぽく、「貸した1000万円を返せ」というAの主張が認められそうです。しかし、この借用書のほかに、「1000万円受領しました。ただし、借入金返済のため。」というA名義の領収書があれば、「すでに返した。」というBの主張に分がありそうです。
もっとも、いくら借用書や領収書があっても、誰かが偽造したものでは話になりません。このため、借用書や領収書などの「文書」を証拠として用いるときは、冒頭に掲げたように、「その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)のです。
このときは、Aは、借用書は、真実、Bが作成した文書だということを、まず、証明しなければなりません。「成立が真正」とは、その文書が、作成者の意思に基づき作成されたという意味です。
では、それをどのようにして「証明」すればよいのでしょうか。そこで登場するのが、民事訴訟法228条4項の「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定です。これがあるので、「ハンコは怖い!」のです。
次回は、民事訴訟法228条4項について説明します。
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」(民事訴訟法228条4項)
「真正に成立した」とは、その文書が、作成者の意思に基づき作成されたという意味です。「推定」とは、甲という事実があれば、乙という事実があると一応、判断するという意味です。ここで「一応」と断ったのは、乙という事実は存在しないという証明がなされると、甲という事実があっても、乙という事実があるとは判断しないという余地があるためです。
話しを文書成立の真正に戻しましょう。上に示した民事訴訟法228条4項は、「本人又はその代理人の署名又は押印がある」(甲という事実に相当)ときは、私文書は「真正に成立したものと」一応、判断するといっているわけです。
AがBに、「半年前に貸した1000万円を返せ。」と主張し、Bが「カネなど借りていない。」と争ったので、Aが、B名義の借用書を証拠として提出したとします。このとき、Aは、この借用書という「文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。」(民事訴訟法228条1項)わけですが、この借用書に、B「本人又はその代理人の署名又は押印がある」なら、民事訴訟法228条4項によって、この借用書は「真正に成立したものと」一応、判断されます。つまり、Aは、借用書の「成立が真正であることを証明しなければならない」という負担から解放されるわけです。Aにとっては、ありがたいことです。
とはいえ、この借用書は、本当は偽造文書で、「真正に成立したもの」ではないということもありえます。しかし、このときは、Bが、「真正に成立したもの」ではないことを証明しなければなりません。Bにとっては、迷惑な話です。証明も簡単ではありません。
だから、安易にハンコを押すと、後で大変な目に遭うことがあるのです。ハンコは怖いのです。このことは、また次回に説明します。
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
タイトルタイトル
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
タイトルタイトル
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント